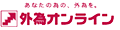消費者物価指数とは物品とサービスの価格の変動率のことです。例として、消費者物価指数(前月比)が0.3%だったときは、物価が前月よりも0.3%上がったことを示しています。
FXでは原則、米国の消費者物価指数が予想よりも高いとドル高円安になり、予想よりも低いとドル安円高になりやすいのです。ただし、インフレの状況で上がったり、デフレの状況で下がると、経済に悪影響があるために米ドルは売られます。
また、消費者物価指数にはコア指数という別の指標が存在します。物品の中でも食料品とエネルギーは気候や為替の影響で物価変動率が激しいため、コア指数はそれらを除いた安定的な物価指数のことを指しており、総合指数よりもインフレ・デフレ基調を判断しやすいものとなっています。

インフレとデフレを消費者物価指数で知る

消費者物価指数は米国に限らずに日本やカナダなどでも、毎月発表される経済指標です。
発表される数字は基準値を「0%」や「100」として、前年比や前月比などと比べて、物の価格が上がり貨幣の価値が下がるインフレ傾向、もしくは物の価格が下がり貨幣の価値が上がるデフレ傾向を判断します。
各国の政府はインフレやデフレが経済に与える影響が大きいために、消費者物価指数などのインフレ系の指標を重要視しています。
インフレが与える影響

インフレになる要因の1つは賃金の上昇です。基本給、歩合給、時給などのベースの単価が上がると、自然と財布の紐が緩くなり、消費が増加していきます。その結果、値段を高くしても売れるために物価も上がります。
企業も利幅が大きくなって利益が確保できると、消費者の給与も上がっていきます。インフレの影響はすぐに賃金には反映されませんが、適度なインフレは国民全体が豊かになる基盤を作ってくれます。
ただ、零細企業や下請けではインフレが給料アップに繋がるまでに、1~2年以上のタイムラグが出ることがあります。その間に景気が悪化すると、インフレの恩恵を受けられずに給与は上がりません。そのため、インフレ率は2%程度を維持することが重要になります。
デフレとの関係

デフレとはインフレの逆であり、インフレよりも厄介な問題です。デフレの要因は主に賃金の減少であり、そのきっかけは物品やサービスが売れなくなることです。
商品需要がなくなると、物の価値が下がり、高い値段では物が売れないため、物価を下がっていくわけです。物価が下がると一時的には私たちは嬉しいですが、手放しで喜んでもいられないのです。
それは安い物をたくさん売っても利幅が少ないため、その物品やサービスを提供する会社の利益が少なくなるなり、従業員の給与も減ります。これが1~2年の短期で終了するなら、デフレはそこまで問題ありません。